「めんどくさいがなるなる100の科学的な方法」の著者である、菅原道仁先生は脳神経外科医であり、脳の機能について一番詳しい職業の先生と言っても過言では無い。
脳には癖があり、その癖を活かすことが自分の行動をコントロールする上でとても重要になる。脳が嫌がる方法で自分をコントロールしようとしても、脳は答えてくれないのだ。
今回は仕事が捗らない理由を脳の立場から2つ解説する。
マルチタスクをしている
2つ以上の仕事を同時にこなしている
マルチタスクができる人というのは、かなり仕事のできる人のイメージである。様々な案件を瞬時にさばいていてかっこいい印象を持つかも知れない。しかし、マルチタスクをしていると人間の脳は驚きの振る舞いをするのだ。
実は、マルチタスクをしている時、人間の脳は集中力が40%お落ちているという。集中力が落ちているということは、エラーやミスが起きやすいと言うことだ。これを二重課題干渉という。なぜこんなことが起きるのか。
マルチタスクをしている時、2つのことを同時にこなしているようで、実は片方を少しさばいて、次に注意を片方に向けて少しさばく、また元の課題に戻って…ということを繰り返しているらしい。ようは注意を向ける対象を高速で切り替えているのだ。人間は1つのことに集中するときに大きな能力を発揮する。注意を頻回に切り替えていると、集中することができず、1つの課題にのめり込むことができない。よってエラーが起きる。
ついでに、注意を切り替えるという行為にも脳はかなりのエネルギーを消費するのだ。マルチタスクを難なくこなしているように見える人は、この多大なエネルギーを無駄に使って、普段よりエラーを出しながら仕事をしているのである。これで普通に仕事ができる人は、1つのことに集中すればもっと成果を出すことができるだろう。
ちなみにマルチタスクを続けると、脳の記憶をつかさどる部分にダメージを与えるコルチゾールが増えることも分かっている。マルチタスクをすることは仕事効率的にも脳の機能的にも良いことは1つも無い。
ながら仕事をしている
近年新型コロナウイルスの流行により自宅での勤務、リモートワークが各社で導入されている。自宅での勤務となれば、仕事の進行を邪魔するようなものがたくさんあり、ながら仕事になりがちだ。その筆頭と言えばスマホである。会社であれば人の目もあり、そう頻回に長時間スマホを触ってもいられないのだが、自宅であればそうはいかない。誰も咎める視線をくれる人がいないので、スマホもさわり放題なのだ。
例えば、PCで資料を作りながらSNSをチラ見、通知が鳴ったらLINEを開き、ついでにyoutubeを流しながら仕事をする…。こうした環境では、先ほど説明した「注意の切り替え」が頻発し、脳は大量のエネルギーを消費する。
しかも、スマホやSNSは脳の報酬系を刺激するため、「もう少し見たい」「次も気になる」と中毒性がある。短時間のつもりが、気づけば30分以上スマホをさわっていた、という経験は誰にでもあるはず。
結果として、仕事の進行は大幅に遅れ、「時間はかけているのに成果は出ない」という感覚に陥ってしまう。
脳の性質を無視した働き方をしている
マルチタスクや、ながら仕事は典型例だが、それ以外にも「脳の特性を無視した働き方」は存在する。
長時間の作業を続ける
脳の集中力にはリミットがある。研究によれば、人間が高い集中力を保てる時間はおよそ90分。それを超えると脳は休息を求め、エラー率が高まる。
しかし、多くの人は「休まずやることが美徳」と考え、長時間机に張り付いて作業を続けようとする。結果として効率がどんどん下がり、1時間で終わるはずの仕事に2時間も3時間もかかってしまう。
ポモドーロ・テクニックのように、25分作業+5分休憩 のサイクルを取り入れるだけでも、脳のパフォーマンスは格段に上がる。
完璧主義に陥る
脳は「完璧を追求する作業」に対して大きな負荷を感じる。細部までこだわりすぎたり、何度もやり直したりすることで、実際の進行は大幅に遅れる。
しかも「まだ不十分だ」という不安がストレスホルモンを増加させ、脳を疲弊させる。これは自己効力感(自分はできるという感覚)を下げ、結果的にモチベーションの低下にもつながる。
まとめ:脳に優しい働き方を選ぶ
「仕事が捗らないのは自分の努力不足」と考えてしまいがちだが、実は脳科学的に見れば 脳の特性を無視しているだけ の場合が多い。
- マルチタスクやながら仕事は効率を下げ、脳に負担を与える
- 集中力には時間のリミットがある
- 完璧主義は脳を疲弊させ、成果を遠ざける
大切なのは「脳の癖」を理解し、その特性に合った働き方を選ぶこと。
シングルタスクで一つのことに集中し、適度に休憩を入れ、完璧ではなく「まず形にする」ことを優先する。こうした工夫だけで、仕事のスピードも質も格段に上がる。
脳科学を味方につけて、無理なく成果を出す働き方を実践していきたいものだ。

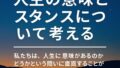

コメント