慢性的なだるさは、西洋医学においても診断が難しい場合が多い。そのような際に補助的治療として漢方薬が注目される。漢方は個々の体質に基づき「気・血・水」の調和を重視するため、西洋医学では説明のつかないだるさに対しても有効である可能性がある。
1. 漢方における「だるさ」の捉え方
漢方では「気虚」「血虚」「水滞」などの概念で倦怠感を説明する。
- 気虚:全身のエネルギー不足により、易疲労・息切れが出現する。
- 血虚:血の不足によりめまい・顔色不良・だるさが現れる。
- 水滞:体内の水分代謝異常により、むくみや重だるさが出現する。
2. 代表的な処方
- 補中益気湯:気虚による慢性疲労に用いられる。
- 十全大補湯:術後や病後の体力低下時に処方される。
- 六君子湯:胃腸虚弱による食欲不振やだるさに適応する。
- 人参養栄湯:高齢者の体力低下や全身倦怠に用いられる。
3. 漢方の利点
- 体質や症状全体を捉える全人的アプローチ
- 西洋薬と併用できる場合が多い
- 長期的な体質改善に有効である可能性がある
4. 注意点
漢方にも副作用は存在する。甘草含有薬による偽アルドステロン症、肝機能障害などには留意が必要である。また効果発現に時間を要するため、即効性を求める場合には不向きである。
結論:だるさに対する漢方の有効性は一定の根拠があり、体質に合わせて選択される必要がある。西洋医学と併用することで相互補完的な効果が期待できる。
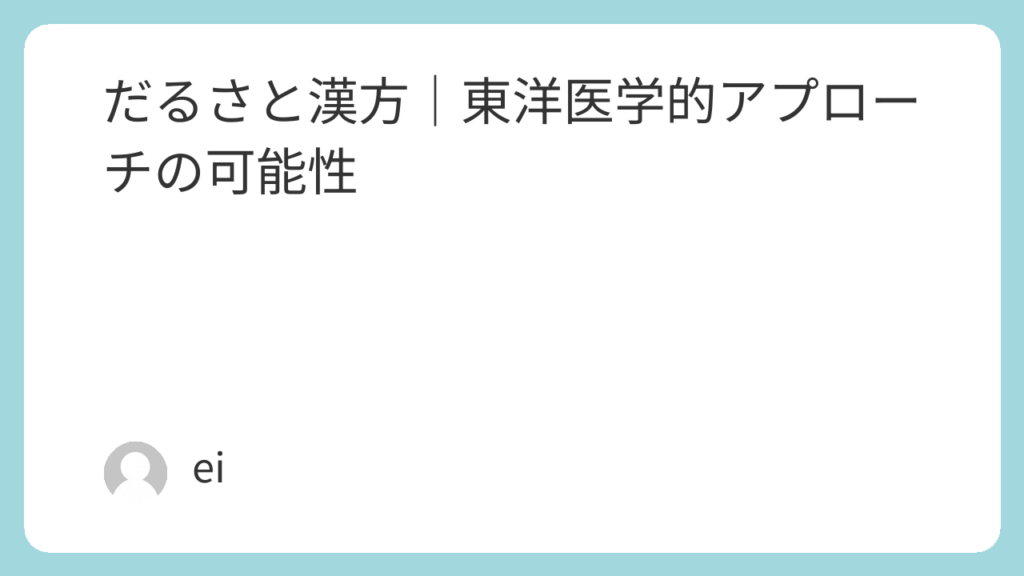
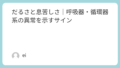
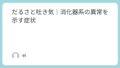
コメント