男性が訴える「だるさ」は、単なる疲労や生活習慣の乱れだけでなく、ホルモン変化や慢性疾患の影響を含む場合が多い。特に中高年期に入ると体力低下やホルモン分泌の変化が顕著となり、だるさが生活の質を大きく損なうことがある。
1. 男性ホルモンの影響
男性ホルモン(テストステロン)は筋肉量や意欲に深く関わる。
- LOH症候群(加齢男性性腺機能低下症候群):40〜50代以降の男性で発症しやすく、だるさ、気力低下、抑うつ傾向を呈する。
- テストステロン低下は筋肉量減少や骨密度低下にもつながり、倦怠感を悪化させる。
2. 生活習慣病との関連
男性は働き盛りの時期に不規則な生活を送りやすく、生活習慣病のリスクが高い。
- 糖尿病:インスリン抵抗性によりエネルギー利用が阻害され、慢性的な倦怠感が出現する。
- 高血圧・脂質異常症:血流障害により全身の活力が低下する。
- 肥満:睡眠時無呼吸症候群や関節負担増大により疲労感を増強させる。
3. 労働環境とストレス
日本の男性は長時間労働や過重な責任を抱えることが多く、慢性的なストレスが倦怠感の温床となっている。
- 睡眠不足と過労
- メンタルヘルスの不調(うつ病、不安障害)
- 飲酒・喫煙による体力低下
4. 男性特有の視点
男性は自覚症状を軽視し、受診を遅らせる傾向がある。だるさを「歳のせい」「仕事のせい」と放置することで、疾患の発見が遅れることが少なくない。
結論:男性におけるだるさはホルモン低下や生活習慣病の影響が大きく、放置すると重大な健康障害につながる。早期に受診し、生活習慣改善と必要な治療を行うことが重要である。
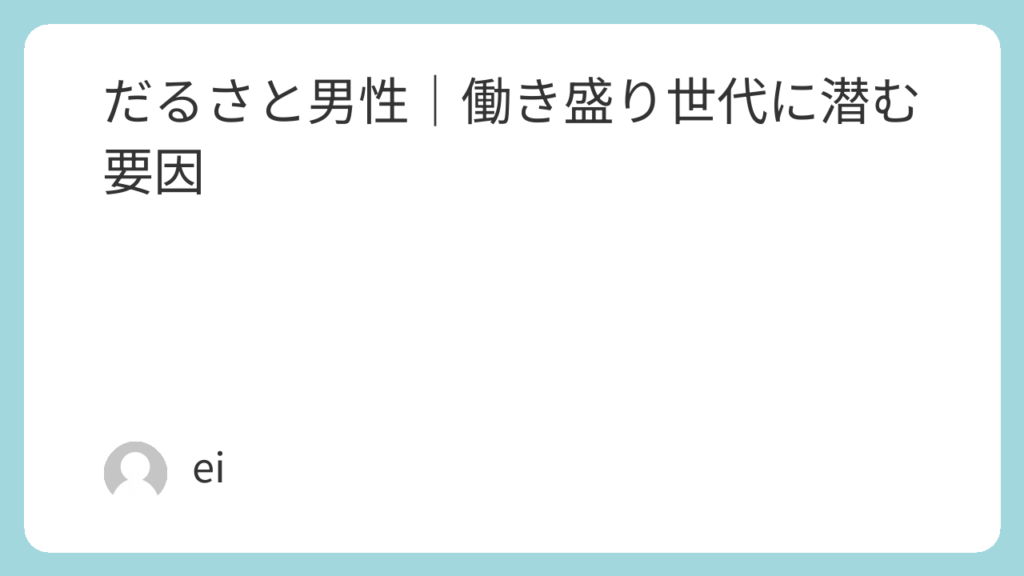
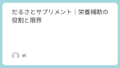
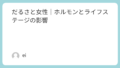
コメント